今回の見学会は、日本の太古の王権体制発祥の地である大和の纒向遺跡、古代の古墳の代表格であり、王権の権威高揚の目的も察せられる百舌鳥古墳群の中でも日本最大の仁徳陵をま近にて体験でき、新たなる歴史認識、見識を深められた。纒向遺跡より出土の古代の人々として当時入手可能であった諸材料でもって知恵を絞り作成した、生活必需品には感激させられた。また、当時の人々の真摯なる、生命観、宇宙観を肌で感じられることができ、遠く太古の人々への思いを寄せる良い機会であった。

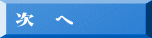
大和王権発祥の地とされる、纒向遺跡よりの出土品を展示してある桜井市立埋蔵文化財センターの常設展示場である。縄文時代の土器、弥生時代の土器、古墳時代の土器といわゆる古代の生活必需品としての器具、農耕具、祭祀器具が展示してあり、古代の生活者の姿が目にみえるようである。
箸墓古墳、大和の地における盟主的古墳で、3世紀後半に建造された古墳としては最大級である。墳長278m、高さ30mを誇り、大和の神として祭られている三輪山の麓にあり、最近では卑弥呼の墓ともいわれる古墳である。
大山古墳陵、いわゆる仁徳天皇陵であるが、河内平野にある百舌鳥古墳群の中でも最大の、というより日本最大の前方後円墳で墳長486m、高さ35mという威容を誇る古墳である。古墳の現状としてはまさに太古の山としか表現の方法が無い。
全体解説

